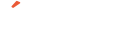外国人児童生徒等の日本語指導
- eラーニング

東京学芸大学が作成した、喫緊の教育課題についての研修動画です。
公益社団法人日本語教育学会「文部科学省委託 外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラムの開発事業」で開発された、資質・能力の「豆の木」モデルに基づき、「新規担当者対応の基本的内容を中心とする」「経験、立場の違いを考慮した内容を含める」「外国人児童生徒等教育の専門性向上を、教師としてのキャリア形成上に位置付ける」ことを基本的な方針として内容を構成しました。
特に、日本語指導経験の浅い教員が抱く困難や課題を想定し、研修外国人児童生徒等の置かれた状況、学校の取組の実例、具体的な指導方法、社会的制度的背景に関する内容をコンテンツに豊富に盛り込んで作製しました。
■講師:見世 千賀子(東京学芸大学 准教授) / 原 瑞穂(上越教育大学) / 齋藤 ひろみ(東京学芸大学 教授), 谷 啓子(東京学芸大学 特任准教授), 小西 円(東京学芸大学 准教授), 工藤 聖子(東京学芸大学 専門研究員)/齋藤 ひろみ(東京学芸大学 教授), 齋藤 ひろみ(東京学芸大学 教授), 米本 弘明(東京学芸大学 准教授)
■主な対象:
・外国人児童生徒等教育・日本語指導経験 1~3年
・学校で外国人児童生徒等の教育に携わっている教諭、講師、教育委員会等派遣の日本語支援員・母語支援員
・幼稚園、小・中学校、高等学校
■紐づく資質・能力と獲得ポイント
(カテゴリA)A-3.子どもや学校をめぐる現代の課題:4ポイント
(カテゴリC)C-1.指導計画・授業づくり:2ポイント
(カテゴリD)D-1.児童生徒理解に基づく指導・支援:2ポイント
(カテゴリE)E-1.個の理解に基づく計画的な指導・支援:2ポイント
(カテゴリF)F-2.多職種協働:2ポイント
公益社団法人日本語教育学会「文部科学省委託 外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラムの開発事業」で開発された、資質・能力の「豆の木」モデルに基づき、「新規担当者対応の基本的内容を中心とする」「経験、立場の違いを考慮した内容を含める」「外国人児童生徒等教育の専門性向上を、教師としてのキャリア形成上に位置付ける」ことを基本的な方針として内容を構成しました。
特に、日本語指導経験の浅い教員が抱く困難や課題を想定し、研修外国人児童生徒等の置かれた状況、学校の取組の実例、具体的な指導方法、社会的制度的背景に関する内容をコンテンツに豊富に盛り込んで作製しました。
■講師:見世 千賀子(東京学芸大学 准教授) / 原 瑞穂(上越教育大学) / 齋藤 ひろみ(東京学芸大学 教授), 谷 啓子(東京学芸大学 特任准教授), 小西 円(東京学芸大学 准教授), 工藤 聖子(東京学芸大学 専門研究員)/齋藤 ひろみ(東京学芸大学 教授), 齋藤 ひろみ(東京学芸大学 教授), 米本 弘明(東京学芸大学 准教授)
■主な対象:
・外国人児童生徒等教育・日本語指導経験 1~3年
・学校で外国人児童生徒等の教育に携わっている教諭、講師、教育委員会等派遣の日本語支援員・母語支援員
・幼稚園、小・中学校、高等学校
■紐づく資質・能力と獲得ポイント
(カテゴリA)A-3.子どもや学校をめぐる現代の課題:4ポイント
(カテゴリC)C-1.指導計画・授業づくり:2ポイント
(カテゴリD)D-1.児童生徒理解に基づく指導・支援:2ポイント
(カテゴリE)E-1.個の理解に基づく計画的な指導・支援:2ポイント
(カテゴリF)F-2.多職種協働:2ポイント
学んでほしいこと
- 外国人児童生徒等の歴史的・社会的背景を知り、文化間移動と発達の視点から外国人児童生徒等の実態を多面的に把握し、かれらがもっている力を発揮して日本語・教科学習や異文化適応を円滑に進められるように指導・支援することの重要性を理解すること。
- 外国人児童生徒等の実態に応じ、日本語指導・教科学習支援を計画・実施し、評価を行うために必要な、言語教育に関する専門的知識と、日本語指導の方法を具体的に学び、校内連携や地域連携を推進して、よりよい学習環境を整備する必要性を知ること。
- 外国人児童生徒等を共生社会の一員として捉え、その教育を保障することの重要性を認識するとともに、周囲の子どもとの相互作用の機会を設け、学校の多文化共生を実現することの重要性を理解すること。
価格 ¥3000(税抜) / ¥3300(税込)
リフレクションシート