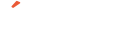- 集合研修

日時
2024年12月7日(土)13:00~17:30
講師
中田 一朗太(株式会社Dmelt)
中村 謙斗(NPO学び足しデザイン工房 aiEDU JAPAN プロジェクト)
山下 雅代(東京学芸大学先端教育人材育成推進機構)
主な対象
現職教員、教職希望の学生、教育関係者
※16歳未満は参加不可
募集人数
50名(開催最小人数2名)
※応募多数の場合は抽選(学校教育関係者を優先します)
場所
対面開催
東京学芸大学小金井キャンパス 大学院アクティブラーニングセンター4階AL3
(お申込みをされた方はページ下段 会場案内図「ダウンロード」ボタンを押下いただき、案内図をダウンロードの上ご確認ください。)
スケジュール
13:00~13:10 趣旨説明(山下雅代)13:10~14:45 生成AIの基本的な仕組みとAIアプリの活用方法(中田一朗太)
生成系AIの基本的な仕組みを座学形式で学習し、その後、実際にAIを利用する体験を通じて理解を深めます。
15:00~16:35 AIリテラシーとディスカッション(中村謙斗)
アメリカの非営利団体aiEDUが開発したAIリテラシー教材「AI Snapshots」を使用し、AIを正しく活用するためのポイントについてディスカッションを交えながら考察します。
16:50~17:30 AIフィードバックの体験とディスカッション(中田・中村・山下)
AIフィードバックを体験し、AIの教育現場での活用の可能性についてディスカッションします。
申込期間
2024年10月10日(木)~2024年12月3日(火)
受講生への連絡事項
PC持参、できるだけGoogleアカウントを事前に取得してご参加ください。
■趣旨■
教育現場でのAI活用が進む中、AIを理解し、教育現場での実践的な知識を身に付けることは非常に重要です。生成系AIは、文章や画像の生成、子供たちの書いた振り返りへのフィーバドックなど、さまざまな教育支援ツールとしての可能性を持っています。このワークショップでは、生成系AIの基本的な仕組みと活用のためのリテラシーを学び、教育現場での活用方法について考えることを目的にしています。
まず、生成系AIの基本的な仕組みを座学形式で学習し、その後、実際にAIを利用する体験を通じて理解を深めます。加えて、アメリカの非営利団体aiEDUが開発したAIリテラシー教材「AI Snapshots」を使用し、AIリテラシーを高め、AIを効果的かつ倫理的に活用するためのポイントについてディスカッションを交えながら考察します。
この機会に、生成系AIを実際に体験し、教育の質を向上させるための活用方法を一緒に考えてみませんか?
(カテゴリA)A-1.教科教育を支える学問的専門性:2ポイント
(カテゴリA)A-2.学習に関する諸学問の知見:2ポイント
(カテゴリB)B-4.人材育成への貢献:2ポイント
(カテゴリB)B-5.教育データとICTの活用:6ポイント
- 生成AIの基本的な仕組み
- AIを使う上でのリテラシー
- AIアプリの活用方法